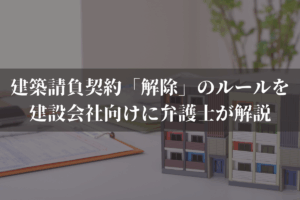建設業で必要な契約書「工事請負契約書」作成のポイントは?弁護士がわかりやすく解説

建設業を営む場合、さまざまな場面で契約書を締結する必要が生じます。特に、工事を請け負う際や工事を下請企業に発注する際には工事請負契約書の締結が必要であり、これを締結せずに工事をすることは建設業法に違反するのみならず、さまざまなトラブルの原因となり得ます。
では、建設業で工事請負契約書を交わさない場合、具体的にどのようなリスクが生じるのでしょうか?また、建設業の工事請負契約書は、どのようなポイントを押さえて作成すればよいのでしょうか?今回は、建設業法における工事請負契約書の概要や工事請負契約書を交わさない場合に生じ得るリスク、建設業で工事請負契約書を作成するポイント、建設業の契約書の作成方法などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設業を営む企業のサポートに特化しており、契約書の作成についても豊富な支援実績を有しています。建設業の契約書作成についてサポートを受ける弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
建設業で必要な「工事請負契約書」とは?
工事請負契約書とは、工事の受発注にあたって取り交わす契約書です。元請企業が施主から工事を請け負う場合はもちろん、請け負った工事の一部を下請企業に発注する際にも、工事請負契約書を交わさなければなりません。
工事請負契約書は書面で取り交わすことが多いものの、近年では電子契約で取り交わすケースも散見されます。
建設業で工事請負契約書を交わさない場合に生じ得るリスク
工事請負契約書は「建設業法上の義務だから作成する」という意味合いもあるものの、それ以上に重要なのは、トラブル発生時に自社の身を守ることにあります。ここでは、建設業で工事請負契約書を交わさない場合に生じ得るリスクを4つ解説します。
- 建設業法違反となる
- 契約内容が不明瞭となり、トラブルに発展する
- 工事の中途解約時の報酬額についてトラブルとなる
- 未払い発生時の回収のハードルが高くなりやすい
とはいえ、自社だけで工事請負契約書を作成することについて、ハードルが高いと感じる場合もあるでしょう。その際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は、建設業で必要な契約書の作成やレビューについて豊富なサポート実績を有しています。
建設業法違反となる
所定の事項が記載された工事請負契約書を取り交わすことは、建設業法上の義務です(建設業法19条)。
工事請負契約書を締結しなかったからといって、すぐに懲役や罰金などの刑事罰が適用されるわけではありません。ただし、工事請負契約書を交わさない場合、指導や監督、公表などの行政処分の対象となり得ます。また、指導などに従わなかった場合、許可の取り消し処分が下るなど重大な結果を招く可能性もあります。
契約内容が不明瞭となり、トラブルに発展する
建設工事の受発注時に契約書を取り交わしていなければ、契約内容が不明瞭となりかねません。そのため、取り決めた報酬内で施工する工事の範囲について齟齬が生じ、トラブルに発展するおそれがあります。
たとえば、複数棟がある工場の第1棟と第2棟だけについて屋根の塗装工事を請け負ったという認識でいるところ、後に施主から「その報酬内で、第3棟も施工するという取り決めだった」などと主張されるおそれがあるでしょう。このような場合には明確な契約書がなければ「言った・言わない」の問題となり、解決が困難なものとなりかねません。
工事の中途解約時の報酬額についてトラブルとなる
さまざまな事情により、工事が完成前に解約される場合があります。たとえば、施主の新社屋の建築を請け負ったものの、その後施主側の経営方針が変わり新社屋建築を見送ることになった場合などです。
このような場合、注文者(施主)はいつでも請負契約を解除できる一方で、請負人である建設会社に生じた損害を賠償しなければなりません(同641条)。この「損害」には、その時点までに支出した材料の購入代金や下請企業への報酬などのほか、解約されなければ得られたはずの利益額も含まれると解されています。
とはいえ、実際に解除による損害額を客観的かつ明確に算定するのは容易ではないでしょう。工事請負契約書でその損害金の算定方法などについて定めがない限り、損害金をいくらとすべきかについて施主との間でトラブルになる可能性があります。
未払い発生時の回収のハードルが高くなりやすい
大前提として、契約書がないからといって契約が成立しないわけではなく、口頭による合意であっても契約は成立します。そのため、工事請負契約書がなかったとしても工事の受発注があったのであれば、当然に報酬請求権も発生します。
とはいえ、工事範囲や報酬額を明確にした契約書などの書面がなければ、万が一報酬が期日までに支払われなかった場合に、報酬を回収するハードルが高くなりかねません。なぜなら、裁判上で報酬を請求するためには「契約が成立していたこと」や「報酬について合意があったこと」などを証明する必要があるものの、契約書がなければ見積書やメールのやり取りなどをかき集めてこれらを証明する必要が生じるためです。
建設業が取り交わす工事請負契約書に記載すべき事項
工事請負契約書に記載すべき内容は、建設業法で定められています。建設業法により、工事請負契約書への記載が要請される内容は次のとおりです(建設業法19条1項)。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
なお、これらはあくまでも必須の記載事項であり、これら以外の項目を記載できないわけではありません。そのため、後のトラブルを避けるためは、必要に応じて他の条項も設けるべきでしょう。
アクセルサーブ法律事務所は建設会社様のサポートに特化しており、いざという時に自社の身を守る契約書の作成支援が可能です。契約書の作成でお悩みの建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
建設業で工事請負契約書を作成するポイント
建設業で工事請負契約書を作成する場合、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?ここでは、主なポイントを4つ解説します。
- 工事の範囲・仕様を可能な限り明確にする
- 追加工事への対応を明確にする
- 工事が遅延した場合の損害金を明確にする
- 中途解約時の報酬算定方法を明記する
工事の範囲・仕様を可能な限り明確にする
1つ目は、工事の範囲や仕様を可能な限り明確にすることです。
先ほど解説したように、合意したはずの工事の範囲や仕様について齟齬が生じれば、トラブルの原因となりかねません。そのため、工事請負契約書では、工事範囲や仕様を可能な限り明確にしておくべきでしょう。
仕様は、契約書に直接記載するのではなく、別紙を添付する形をとることが一般的です。
追加工事への対応を明確にする
2つ目は、追加工事への対応を明確にすることです。
当初取り決めた工事以外の工事をする必要性が生じた場合、追加報酬を請求できるのが原則です。しかし、施主側としては、たとえば「自分は家1棟を建てることを発注したのであり、たとえば地中に埋設物が見つかったとしても、それは建設会社側で工夫して対応すべき問題だ」などと考えている可能性もあります。
そのため、認識の齟齬をなくすためにも、追加工事の必要性が生じた場合には別途報酬が発生することや、報酬額については別途相談して取り決めるべきことなどを記載しておくとよいでしょう。
工事が遅延した場合の損害金を明確にする
3つ目は、工事が遅延した場合の損害金を明確にすることです。
天候不順などの影響で、工事が遅延する可能性はゼロではないでしょう。その場合、建設会社から施主に対して賠償金を支払う必要が生じる可能性があります。たとえば店舗の建築であれば引き渡し日に合わせてオープン日を決める場合もあり、引き渡し日が遅れれば営業開始日が遅れて施主側に損害が生じる可能性があるためです。このような場合、「適正な損害賠償額がいくらであるのか」についてトラブルになるかもしれません。
契約書に万が一引き渡しが遅れた場合における1日ごとの損害金を明記しておくことで、原則として契約書の記載に応じて損害額を算定することとなり、トラブル回避につながります。
中途解約時の報酬算定方法を明記する
4つ目は、中途解約時の報酬算定方法を明記することです。
先ほど解説したように、工事請負契約が完成前に解除された場合には損害金やその時点までに完成した部分に対応する報酬の請求が可能であるものの、その額について交渉がまとまらずトラブルとなるおそれがあります。
契約書に中途解約時の報酬額(違約金)の額や具体的な計算方法を記載しておくことで、原則としてその定めに従って金額を算定することとなるため、トラブルを回避しやすくなります。
建設業の契約書の作成方法
建設業の契約書は、どのように作成すればよいのでしょうか?ここでは、契約書の3パターンの作成方法を解説します。
- 国土交通省の「建設工事標準請負契約約款」をそのまま活用する
- インターネットでテンプレートを探して活用する
- 弁護士に依頼して作成する
国土交通省の「建設工事標準請負契約約款」をそのまま活用する
1つ目は、国土交通省が公表している「建設工事標準請負契約約款」をそのまま活用する方法です。
国交省では、建設工事の受発注に活用できる「建設工事標準請負契約約款」を公表しています。この約款には法律上記載が求められている項目が漏れなく盛り込まれており、これを活用することで建設業法の基準を満たすことが可能となります。
しかし、これはあくまでも一般的なケースを想定した一例であり、契約の実態に適している保証はありません。契約実態と合わない契約書を交わすことは、トラブルの原因となり得ます。
そのため、建設工事標準請負契約約款を活用するのであれば内容を正しく理解したうえで、自社の契約実態に合う内容かついざという時に自社の身を守れる内容へと作り変える必要があります。
インターネットでテンプレートを探して活用する
2つ目は、インターネットで契約書のテンプレートを探し、これを活用する方法です。
インターネットで探せば、工事請負契約書などのサンプルが見つかるかもしれません。これをそのまま流用すれば、「それらしい」契約書が簡単に作成できるでしょう。
しかし、この方法はおすすめできません。なぜなら、建設工事標準請負契約約款と同じく、その契約書の内容が契約実態に合っている保証はないためです。
また、そのテンプレートに、建設業法が求めている事項が漏れなく盛り込まれているか否かもわかりません。そのため、テンプレートの内容を正しく理解して適宜条項の改訂などができる場合を除き、この方法による作成は避けた方がよいでしょう。
弁護士に依頼して作成する
3つ目は、弁護士に依頼して自社に合った契約書を作成してもらうことです。
建設業で使用する契約書は、弁護士のサポートを受けて作成するのがおすすめです。弁護士に契約書の作成やレビューを依頼すれば費用は掛かるものの、一度基本となる契約書をしっかり作成しておけば、自社が締結する他の工事請負契約への転用も可能となります。
弁護士に契約書の作成やレビューを依頼するメリットについては、次で改めて解説します。
建設業で契約書の作成・レビューを弁護士に依頼するメリット
建設業で、契約書の作成やレビューを弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを3つ解説します。
- 法令に適した契約書が作成できる
- 契約実態に合った契約書が作成できる
- トラブル発生時の対応がスムーズとなりやすい
なお、アクセルサーブ法律事務所は建設業界に特化しており、業界実態を踏まえたより的確な契約書の作成支援が可能です。建設業で使用する契約書の作成についてサポートを受けられる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
法令に適した契約書が作成できる
契約書にさえ記載すれば、どのような条項であっても確定的に有効になるわけではありません。たとえば、施主が消費者である場合には施主の利益を不当に害することとなる条項は消費者契約法の定めにより無効となるおそれがあるなど、関連する法令に適合する内容としなければトラブルの原因となる可能性があります。
また、先ほど解説したように建設業法では工事請負契約書に記載すべき事項が定められており、これを漏れなく記載することも必要です。弁護士に作成やレビューを依頼することで、法令に適合した契約書の作成が可能となります。
契約実態に合った契約書が作成できる
契約実態に合った契約書を、自社だけで作成するのは容易ではありません。しかし、繰り返し解説しているように、契約実態に合わない契約書や不明瞭な契約書を取り交わすことはトラブルの原因となり得ます。せっかく締結した契約書がトラブルの原因となる事態は、避けたいことでしょう。
弁護士にサポートを受けることで、契約実態に合った的確な契約書の作成が実現できます。
トラブル発生時の対応がスムーズとなりやすい
弁護士は、トラブルが発生してから関与することも少なくありません。そして、トラブル解決にあたる中で、「契約書にこのような条項が入っていれば、スムーズに解決できたのに」、「契約書がこのような内容になっていれば、自社に有利な解決をはかれたのに」などと、残念に感じるケースもあります。
契約書の作成にあたっては、このような経験を活かし、トラブル発生から「逆算」をした条項の検討や提案が可能です。そのため、弁護士に契約書の作成やレビューを依頼することで、トラブル発生時にスムーズかつ自社に有利な解決をはかりやすくなるでしょう。
建設業の契約書に関するよくある質問
続いて、建設業の契約書に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
建設業の工事請負契約書に印紙税はかかる?
建設業の工事請負契約書には、原則として印紙税がかかります。貼付すべき印紙の額は契約書の記載した請負金額によって異なり、それぞれ次のとおりです。
| 契約書に記載された契約金額 | 印紙の額(軽減措置の適用後) |
|---|---|
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 1千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 5千円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 50億円超 | 48万円 |
ただし、印紙税は「紙」の契約書にかかる税金であり、電子契約の場合には印紙税はかかりません。
印紙税節約のため契約書の1通はコピーでもよい?
「紙」の契約書で契約を締結する場合、建設業法を遵守するには、原則として原本が2通必要です。なぜなら、建設業法では契約書に「署名又は記名押印を」したものを「相互に交付」することを求めており、この要請を満たすには契約書の原本が2通必要となるためです。契約書の原本を2つ作成する場合、それぞれに印紙を貼付しなければなりません。
建設業の契約書作成はアクセルサーブ法律事務所にお任せください
建設業の契約書作成は、アクセルサーブ法律事務所にお任せください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 建設・不動産業界に特化している
- 契約書の整備など、予防法務に注力している
- 経営者目線での実践的なアドバイスを得意としている
建設・不動産業界に特化している
アクセルサーブ法律事務所は、弁護士の中では珍しく、建設・不動産業界に特化しています。これらの業界における取引実態や生じやすいトラブルなどを熟知しており、これを踏まえたより的確な契約書作成サポートが実現できます。
契約書の整備など、予防法務に注力している
トラブルが生じてしまうと、その対応に時間や人手、精神的な負担が生じ、本業に支障をきたしかねません。そこで、アクセルサーブ法律事務所はトラブルが起きてからの対応のみならず、「トラブルを起こさないための対策」や、「万が一トラブルが生じた際の影響を、最小限に抑えるための対策」に力を入れています。
経営者目線での実践的なアドバイスを得意としている
法的に正しいことと、経営として望ましいことは一致しないことも多いでしょう。しかし、長期的に経営を続けていくためには、法令遵守を避けて通ることは困難です。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産会社の経営実態を深く理解したうえで、法的なルールは守りつつも、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」を重視した経営者目線での実践的なアドバイスを得意としています。
まとめ
建設業で必要となる工事請負契約書について、契約書がない場合に生じ得るリスクや契約書作成のポイント、契約書を作成する方法などを解説しました。
建設業において工事の受発注をする際は、契約書を取り交わしておくべきです。契約書がないまま工事を進めることは建設業法違反にあたるほか、さまざまなトラブルの原因ともなり得るためです。
とはいえ、自社だけで契約実態に適合した的確な契約書を作成することを、ハードルが高いと感じることも多いでしょう。そのような際は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。弁護士のサポートを受けることで法令や契約実態に適合した契約書の作成が可能となるほか、万が一トラブルが発生した際にもスムーズな解決をはかりやすくなります。
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界に特化しており、契約書の作成をはじめとした「予防法務」に力を入れています。契約書の作成でお悩みの建設会社様は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。