建築請負契約「解除」のルールを建設会社向けに弁護士がわかりやすく解説
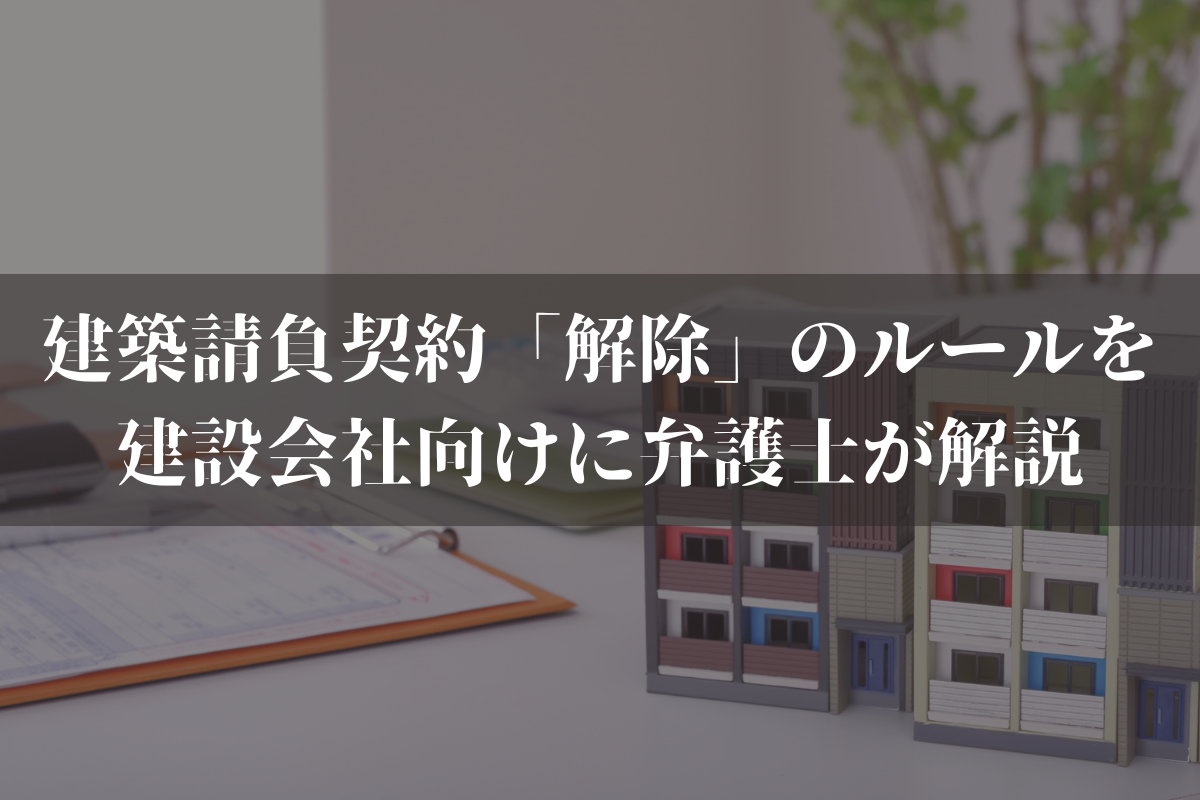
建築請負契約が、途中で解除される場合があります。しかし、建築請負契約の解除にはさまざまなパターンがあり、解除の根拠や解除による損害賠償請求の可否などの判断に迷うことも少なくないでしょう。
では、建築請負契約の解除には、主にどのようなパターンがあるのでしょうか?また、建築請負契約の解除を申し入れられたら、どのように対応すればよいのでしょうか?今回は、建築請負契約の解除のパターンを紹介するとともに、施主から建築請負契約が解除された場合の対処方法や建築会社側から建築請負契約を解除したい場合の対処方法などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は建設・不動産業界のサポートに特化しており、建築請負契約の解除に関するご相談についても豊富な対応実績を有しています。建築請負契約の解除に関してお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。
建築請負契約解除のパターン別の概要
建築請負契約の解除には、主に4つのパターンがあります。はじめに、それぞれの解除の態様について整理して解説します。
- 施主側から、施主都合で解除する
- 施主側から、建設会社の債務不履行を理由に解除する
- 建設会社から、建設会社の都合で解除する
- 建設会社から、施主の債務不履行を理由に解除する
なお、いずれのパターンであっても建設会社側には対応にあたって難しい判断が必要となるため、相手方と直接交渉などを始める前に弁護士にご相談ください。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお問い合わせください。
施主側から、施主都合で解除する
建築請負契約の解除パターンの1つ目は、施主側からの、施主都合による解除です。
民法において、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定められています(民法641条)。そのため、施主は、目的物が完成するまでの間、いつでも契約を解除できます。
ただし、この場合には、施主は建設会社に対して損害を賠償しなければなりません。この「損害」には解除されるまでの間に建設会社が支出した材料費や下請会社への報酬などに加え、その仕事が解除されなければ得られたはずの利益(「逸失利益」といいます)も含まれると解されています。
この損害額を正確に算定するのが困難な場合も多いため、契約書で損害額の算定方法を定めることも少なくありません。契約書に定めがある場合、原則としてその契約書の規定に従って損害額が算出されることになるためです。
施主側から、建設会社の債務不履行を理由に解除する
建築請負契約の解除パターンの2つ目は、施主側からの、建設会社の債務不履行を理由とする解除です。
建設会社側に債務不履行がある場合、施主は原則として事前に一定期間を定めて催告をしたうえで、契約を解除できます(同541条)。ただし、不履行の程度が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除することはできません。
また、債務者(建設会社)がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときなど一定の場合には、事前の催告をすることなく契約の解除が可能です(同542条)。
なお、契約の解除は損害賠償請求を妨げません。そのため、建設会社側の債務不履行により施主側が何らかの損害を被った場合、契約の解除と併せて損害賠償請求がされる可能性もあります。
ただし、請負契約が仕事の完成前に解除された際、請負人(建設会社)が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって施主が利益を受ける場合には、その部分を仕事の完成とみなして報酬請求ができるとされています(同634条)。解除がされた場合は両当事者が原状回復義務を負う(契約がなかったのと同じ状態とする)のが原則であるものの、途中まで作った建物を解除を理由に取り壊すこととなれば社会的な損失が大きいためです。
そのため、仕事の進捗度合いによっては、建設会社側から施主に対して一定の報酬を請求できる可能性もあるでしょう。また、施主からなされた損害賠償請求と建設会社からの報酬請求を一部相殺できる可能性もあります。
建設会社から、建設会社の都合で解除する
建築請負契約の解除パターンの3つ目は、建設会社の側からの、建設会社の都合による解除です。
施主からの解除とは異なり、民法には請負人(建設会社)側から請負契約を自由に解除できる旨の規定はありません。そのため、建設会社側に建築請負契約を解除したい事情が生じた場合には、契約書に請負人から解除できる事由が明記されていない限り、施主との合意による解除を目指すほかないでしょう。
この場合には、建設会社から施主に対して賠償金の支払いが必要となる可能性が高く、その額についても原則として合意により定めることとなります。
ただし、先ほど解説したように、請負が仕事の完成前に解除された場合において、既にした仕事のうち可分な部分の給付により施主が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなしてその部分に応じた報酬が請求できます(同634条)。そのため、たとえば建物が完成間近であるような場合には、建設会社が負担すべき解除による賠償金と、施主が負担すべき途中まで完成した仕事に関する報酬とを相殺できる可能性もあります。
建設会社から、施主の債務不履行を理由に解除する
建築請負契約の解除パターンの4つ目は、建設会社の側からの、施主の債務不履行を理由とする解除です。
相手方の債務不履行を理由とする解除は、施主からのみならず、建設会社側からも可能です。請負契約における施主の主な義務は、報酬を支払うことです。そのため、契約で中間金の支払いなどについて定めた場合に期日までにその報酬が支払われず、催告してもなお支払われない場合などに解除を検討することになるでしょう。
なお、先ほど解説したように、解除権の行使は損害賠償請求を妨げません。そのため、解除と併せて、施主の債務不履行により被った損害金の賠償請求も可能です(同545条4項)。また、完成した仕事の割合に応じて報酬を請求することもできます(同634条)。
施主側から、施主都合で建築請負契約が解除された場合の対処方法
施主側から、施主都合で建築請負契約の解除が申し入れられた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、対応の流れを解説します。
- 解除の理由を確認する
- 中途解約に関する契約書の規定を確認する
- 弁護士に相談する
- 損害賠償請求をする
解除の理由を確認する
施主側から建築請負契約の解除が申し入れられたら、まずはその理由を確認します。
施主から契約が解除される理由はさまざまであり、「家族関係の変化により家を建てる必要がなくなった」「新社屋建設を予定していたが、業績が芳しくないので見送ることにした」など純粋に施主側の都合による場合もあれば、「ローン審査に通らなかった」など外部的な要因である場合もあります。
特に、「ローン審査に通らなかった」などの場合には契約書にローン条項(ローンの審査に通らなければ、無条件で契約を解除できる旨の条項)が入っている可能性もあるなど、解除の理由によって対応方法が異なる可能性もあるため、解除の理由を入念に確認しておきましょう。
中途解約に関する契約書の規定を確認する
契約書で、中途解約時の対応に関する定めを置いていることも少なくありません。そのため、まずは契約書を確認し、中途解約に関する規定を確認しましょう。契約書に中途解約時に請求できる報酬額などについて定めがあれば、原則としてその規定の内容に従って処理されることとなります。
弁護士に相談する
契約書の規定を確認したら、施主側に損害賠償請求をする前に弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、そのケースにおける損害賠償請求の可否や、適正な賠償額などの把握が可能となるためです。
建築請負契約の解除について相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までご連絡ください。
損害賠償請求をする
弁護士に相談した結果を踏まえて、施主に対して解除による損害賠償請求をします。まずは建設会社側から直接損害金の支払いを求め、施主がこれに応じない場合には弁護士が代理で請求する場合が多いでしょう。
弁護士が代理で請求してもなお施主側が支払いに応じない場合や金額について折り合いがつかない場合などには、調停や訴訟などで解決をはかることとなります。
施主側から、建設会社の債務不履行を理由として建築請負契約が解除された場合の対処方法
施主側から建設会社側の債務不履行を理由として契約の解除を申し入れられた場合の対応は、施主都合による解除の場合とは多少異なります。ここでは、債務不履行により解除された場合の対応の流れを解説します。
- 解除の理由となった不履行の内容を確認する
- 弁護士に相談する
- 具体的な対応について交渉する
解除の理由となった不履行の内容を確認する
はじめに、建築請負契約が解除される原因となった「不履行」の内容を確認します。不履行の内容によっては、修補など別の方法で対応でき、解除は免れられる可能性があるためです。不履行の内容を確認したらその不履行が生じた経緯についても確認し、証拠を残します。
弁護士に相談する
続けて、弁護士へ相談します。弁護士へ相談することでそのケースにおける適切な対応方法を把握でき、これを踏まえて施主との交渉を進めやすくなるためです。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
具体的な対応について交渉する
弁護士への相談内容を踏まえ、具体的な対応について施主と交渉します。債務不履行の内容が修補で対応し得るものである場合、建設会社側としては修補で対応できないか交渉することになるでしょう。
また、契約解除(または、修補)と併せて損害賠償請求がなされる可能性もあるため、適正な賠償額も検討します。その一方で、完成部分については報酬を請求できる可能性もあるため、これも含めて交渉を進める必要があるでしょう。
当事者同士では交渉がまとまらない場合、弁護士が代理で交渉したり、調停・訴訟などで解決をはかったりします。
建設会社側から建築請負契約を解除したい場合の対処方法
建設会社側から建築請負契約を解除しようとする場合は、どのように対応すべきなのでしょうか?ここでは、建設会社側からの契約解除の流れを解説します。
- 契約書の規定を確認する
- 相手方の債務不履行の内容を確認する
- 相手方の債務不履行の証拠を残す
- 弁護士に相談する
- 契約書の規定に従って催告する
- 契約を解除する
契約書の規定を確認する
契約書においては、請負人側からの解除事由が定められていることがあります。そのため、まずは契約書を確認し、請負人側からの解除事由が設けられているかどうかを確認しましょう。そのような定めがある場合、今回の事案がそれに当てはまるかどうかを検討することになります。
相手方の債務不履行の内容を確認する
契約書に請負人側からの解除事由がない場合は、施主側の債務不履行の内容を確認します。
先ほど解説したように、契約書に特別の規定がある場合を除き、建設会社側から建築請負契約を一方的に(合意によらずに)解除するには、原則として施主側に債務不履行がなければなりません。そのため、不履行の内容を、具体的に確認するステップが必要です。
相手方の債務不履行の証拠を残す
施主側の債務不履行の内容が確認できたら、これについて証拠を残します。施主側から契約解除は不当であるなどと反論された場合、債務不履行の証拠がなければ契約解除ができなくなったり、施主側から損害賠償請求をされたりするおそれが生じるためです。
弁護士に相談する
続いて、弁護士に相談します。
解除という結果に対して債務不履行の内容が軽微であったり、解除の通知方法に問題があったりすれば、大きなトラブルに発展するかもしれません。そのため、建設会社側からの契約解除は特に慎重に進める必要があり、施主に解除を通知する前に弁護士に相談すべきでしょう。
建設会社側からの契約解除をご検討の際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
契約書の規定に従って催告する
債務不履行による契約解除の方法は契約書または民法で定められており、事前に催告が必要であることが多いでしょう。その場合には、契約解除の通知に先立ち、催告をします。催告とは、不履行になっている債務を履行するよう(たとえば、期限になっても中間金を支払わないのであれば、その中間金を支払うよう)正式に求めることを指します。
契約を解除する際に相手方から「催告をされていない」と主張される事態を避けるため、解除を前提とした催告は、内容証明郵便などで行うことが一般的です。
契約を解除する
催告から一定期間(契約書に期間の定めがある場合には、その期間)を経過してもなお債務が履行されない場合、改めて内容証明郵便を送るなどして正式に契約を解除します。
また、必要に応じて、相手方への損害賠償請求やその時点までにした工事に対応する報酬請求などを行います。
建築請負契約の解除に関して弁護士に相談するメリット
建築請負契約の解除に関して弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。ここでは、弁護士に相談する主なメリットを3つ解説します。
- 状況に応じた具体的な対応を的確に検討できる
- 訴訟に移行した場合の結果を想定して交渉を進められる
- 必要に応じて交渉を弁護士に任せられる
状況に応じた具体的な対応を的確に検討できる
1つ目は、状況に応じた具体的な対応を的確に検討できることです。
建築請負契約の解除について対応を誤ると、大きなトラブルの原因となったり大きな損失を被ったりするおそれがあります。施主から申し入れられた解除に返答をしたり、自社から施主に解除を申し入れたりする前に弁護士に相談をすることで、状況に応じた対応を事前に的確に検討でき、最適な解決をはかりやすくなります。
訴訟に移行した場合の結果を想定して交渉を進められる
2つ目は、訴訟に移行した場合の結果を想定したうえで、施主との交渉を進められることです。
建築請負契約の解除の可否や損害賠償請求の可否、損害賠償の適正額などに関して双方の主張が対立する場合、最終的には訴訟で解決をはかることとなります。弁護士は関連する過去の判例や裁判例、事例などを熟知しており、これを踏まえて具体的な対応策を検討します。
仮に訴訟にまで発展した場合に想定され得る結論を認識しておくことで、「どのあたりで手を打つべきか」などの判断がしやすくなるでしょう。
必要に応じて交渉を弁護士に任せられる
3つ目は、必要に応じて交渉を弁護士に任せられることです。
建築請負契約の解除に関して施主との間でトラブルに発展した場合、自社で直接対応しようとすれば多大な時間と労力がかかります。また、不用意な発言をしたり不用意に書面を取り交わしたりすれば、訴訟において不利となるかもしれません。
弁護士に依頼する場合、弁護士に対応を任せることが可能となります。これにより、不用意に不利な言動をする事態を避けられるほか、トラブル対応に時間や精神力を取られすぎず本業に注力しやすくなるでしょう。
建築請負契約の解除に関するよくある質問
続いて、建築請負契約の解除に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
建築請負契約が施主都合で解除されたら、逸失利益分も請求できる?
建築請負契約が施主都合で解除された場合、逸失利益分も含めて請求できる可能性があります。具体的な金額は解除の状況や契約書の内容などによって異なるため、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。
建築請負契約の解除は口頭でも有効?
建築請負契約の解除は、契約書に解除の方式について別段の定めがない限り、口頭であっても有効です。
ただし、口頭で解除を申し入れる場合、後に「言った・言わない」などのトラブルになる可能性が否定できません。そのため、可能な限り書面での通知をおすすめします。
また、訴訟に発展する可能性があるなどトラブルが予見される場合には、内容証明郵便を用いて解除を通知すべきでしょう。
建築請負契約の解除でお困りの際はアクセルサーブ法律事務所までご相談ください
建築請負契約の解除でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 建設・不動産業界に特化している
- 予防法務に注力している
- 実践的なアドバイスを得意としている
建設・不動産業界に特化している
アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産業界に特化しています。業界における取引実態や生じやすいトラブル類型、関連する判例・裁判例などを熟知しているため、より実践的なサポートが提供できます。
予防法務に注力している
アクセルサーブ法律事務所は最終的なゴールを「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことに設定しています。この目標を達成するため、トラブルが発生してからの対応のみならず、トラブルを防ぐ「予防法務」にも力を入れています。
企業が予防法務に取り組むことで、トラブルに巻き込まれる可能性を最小限に抑えられ本業に注力しやすくなるほか、万が一トラブルが発生した際にも自社の損失を最小限に抑えやすくなります。
実践的なアドバイスを得意としている
法的に望ましいことと経営上望ましいことが、必ずしも一致するとは限りません。しかし、長期的な視点で見れば、法令を軽視することは自社の屋台骨を揺るがす事態になりかねないでしょう。
アクセルサーブ法律事務所は、法的なルールは守りつつ、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」も重視した経営者目線かつ実践的なアドバイスを提供しています。
まとめ
建築請負契約の解除についてパターンごとの概要を紹介するとともに、施主から解除を申し入れられた場合の対応方法や自社から建築請負契約を解除しようとする場合の流れなどを解説しました。
建築請負契約の解除には、主に4つのパターンがあります。それぞれ解除の法的根拠や損害賠償請求の可否などの考え方が異なるため、解除を申し入れられた場合や自社から解除しようとする際は、まずその解除がどのパターンに該当するか検討するとよいでしょう。
相手方との交渉を開始する前には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、そのケースにおける最適な対処法を踏まえて対応に臨むことが可能となります。
アクセルサーブ法律事務所は建築・不動産業界に特化しており、建築請負契約の解除に関するご相談についても豊富な対応実績を有しています。建築請負契約の解除でお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。


